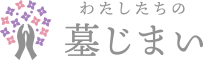お役立ち情報
お役立ち情報 手元供養の法律的な問題は?
前回ご紹介した『墓じまいの流れ』の中で、新しい遺骨の行き先をいくつかあげました。公営墓地(改葬合祀)や散骨、菩提寺(永代供養)、納骨堂、手元供養などがありましたが、今回はその中の手元供養についてご紹介したいと思います。◯手元供養とは取り出した遺骨を自宅で保管する方法で、自宅供養とも呼ばれます。保管方法には、次の2つの方法があります。遺骨・遺灰をすべて保管墓地や寺院へ納骨した上で、一部を自宅で保管どちらを選ぶかは供養に対する考え方で分かれることになると思います。また遺骨を分けて保管することは、仏教では昔から「分骨」という形で一般的に行われているため、問題はありません。◯法律的な問題