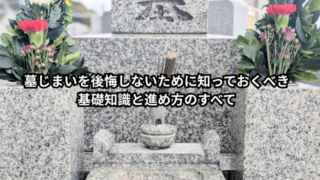 お役立ち情報
お役立ち情報 墓じまいを後悔しないために知っておくべき基礎知識と進め方のすべて
墓じまいとは何か、費用の目安や具体的な流れ、必要な手続き、寺院墓地での注意点までをわかりやすく解説。初めて墓じまいを検討する方でも安心して進められる完全ガイドです。
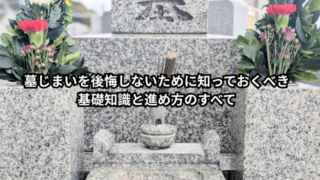 お役立ち情報
お役立ち情報  お役立ち情報
お役立ち情報  お役立ち情報
お役立ち情報  お役立ち情報
お役立ち情報  お役立ち情報
お役立ち情報  お役立ち情報
お役立ち情報