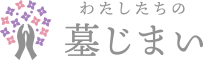すべて
すべて 散骨は法律では認められている?種類・費用相場・注意点のまとめ
さまざまな事情で、お墓を持たない方が増えてきました。お墓に納骨をするという従来の方法の他に、納骨にはさまざまな方法がありますが、その中でも最近注目されているのが「散骨」です。散骨とは名前の通り、粉状にした遺骨を“撒く”方法となっています。最近散骨を選ぶ方は増えてきたものの、まだ日本では少数派となっており、費用相場や手続きなど、不明点がたくさんあるでしょう。そんな散骨の種類や費用相場、注意点などをまとめていきます。散骨とは?特徴を解説