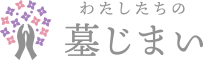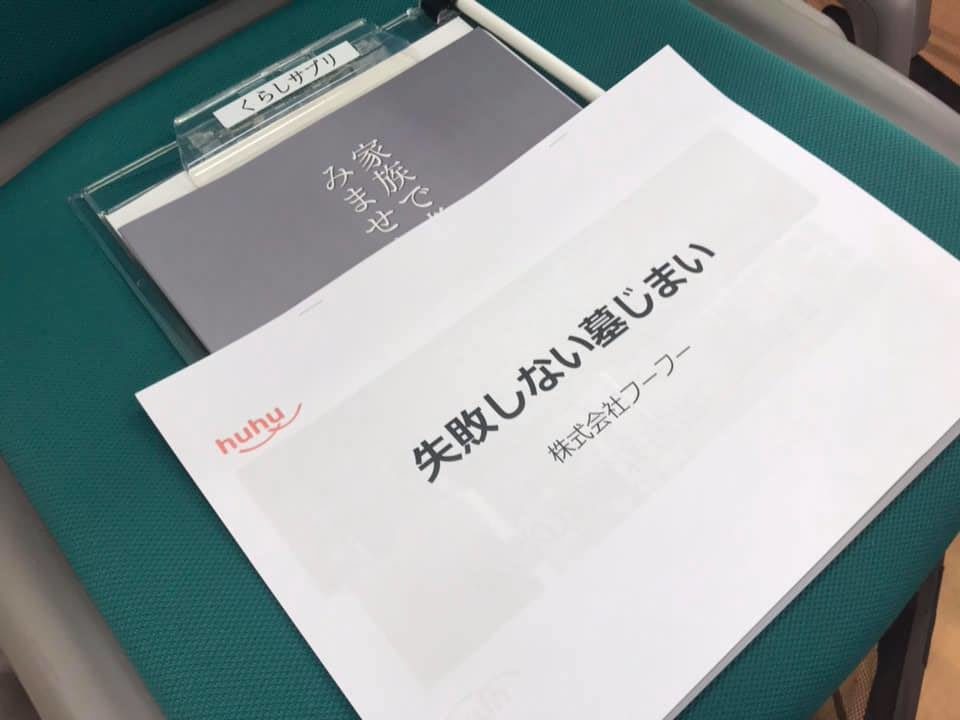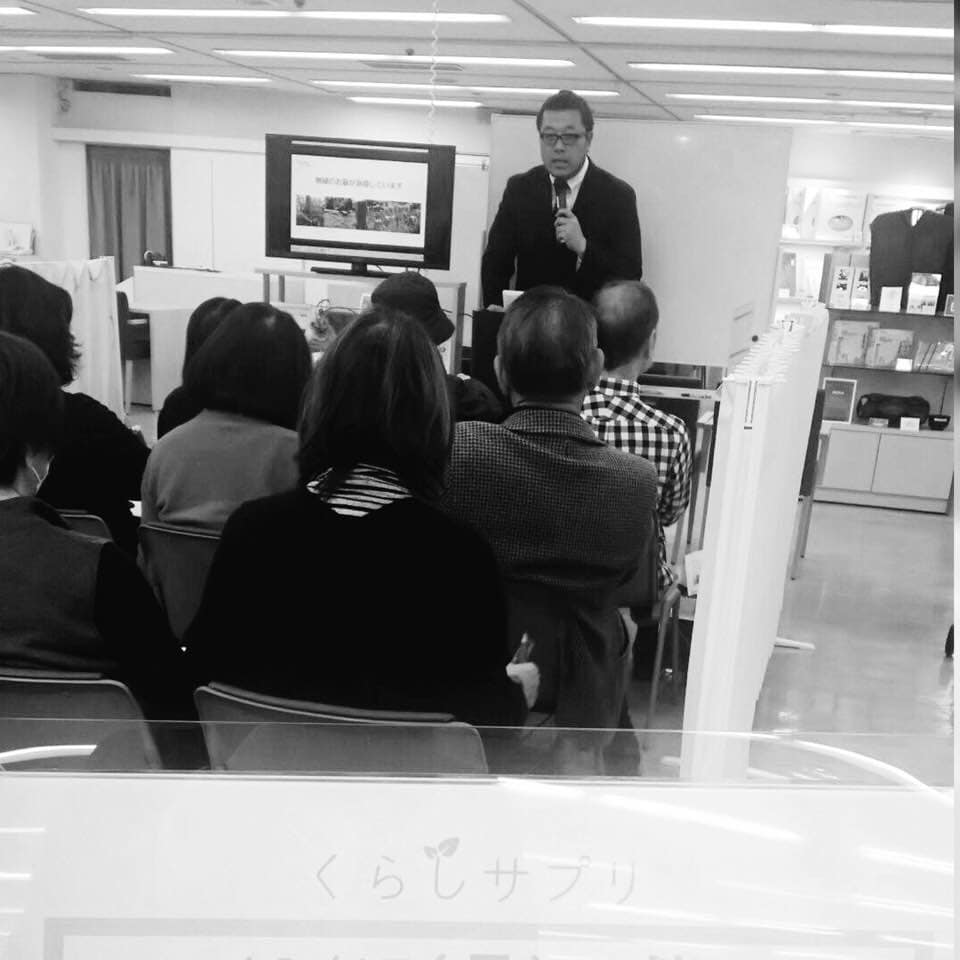墓じまい
墓じまい 夕刊フジ連載1話目「墓じまいの費用・方法について」
少子高齢化、都市部への人口集中と地方の過疎化が進む中、「墓守の不在」や「お墓が遠く、お参りが困難」などの理由により、約20年前から墓じまいが急増しています。厚生労働省の調査によると、2015年の墓じまい(改葬)件数は全国で9・5万件と過去最高になりました。お墓を放置すると、大切な先祖が無縁仏になるだけでなく、遺族に管理料や法要料を請求されることもあるため、墓じまいを決断する方が増えているのです。墓石の撤去費用は、15~80万円程度とバラツキがあります。お墓の広さや立地に左右されるほか、お寺を窓口としてその指定業者に頼むと、相対的に高額となる傾向があります。墓石の撤去料以外にも必要な費用は、主に以下のようなものです。